アコーディオンを習い始めた頃から 今もなお、アコーディオン〈以下、アコ〉とは 全く関係のない昔の経験が、かたちを変えて 思いがけずアコに繋がることは たびたびあります。

自分の好きなこと(私の場合は、アコ)だと 特に繋げて考えたり感じたりし易いのかもしれず、アコでなくとも 人それぞれ そういうものがあるのかなと、また、なんでも同じなのかなと思ったりもします。
今回は 私個人の場合の そうしたことを書いてみようと思います。
(※自身の頭の中の整理·ひとりごとの回です。)
以前の仕事での経験
アコーディオン〈以下、アコ〉と関係のない過去の経験で アコに繋がっていることは いくつもあり、そのなかでも大きいことの1つは 日本語教師の職に就いていた頃の経験なので、このことを書いてみます。
以前の記事では、「型(カタチ)」の観点から この仕事のことに僅かに触れたので、今回はまた少し異なる視点で。
もうずっと前のことですが、数年ほど 都内の日本語学校に勤務し、外国人に日本語を教える“日本語教師”の仕事をしていました。
この経験は、自分のアコクラスを担当させていただくときだけでなく、それ以前に 私自身が生徒としてアコを習っていた頃から とても活きています。
(余談)(※ ココを押下すると 内容が開きます)
ただ、そのときの座学よりも、後の現場(勤務先の日本語学校)での実体験の方が、私にとっては 以外のことも含めて ゆくゆくの諸々に大きく影響しています。
ゆくゆく繋がった主なこと
日本語教師での経験から繋がったことの中から、分かりやすい事柄を いくつかあげてみます。
- ① 習得方法(対象が大人であること)
- ② 人によって異なる響き方
- ③ 手段と目的の意識 / いろいろな目的
(余談)前提:勤務していた日本語学校のコト(※ ココを押下すると 内容が開きます)
したがい、学生の《年齢層》は 最年少でも高卒以上で、当時の私より年上の方々も多く、また、日本語学校 入学時の 日本語の《語学レベル》は、全く日本語が分からない0(ゼロ)の方から、習得途中の方までさまざま。
ちなみに、講師側は 全員、日本語で 日本語を教えていました。(そもそも私は 全くもって英語(外国語)ができませんが、学校の方針で、外国語が話せる職員も、クラスを担当している職員は 日本語以外の使用は禁止されていました!)
→ 当時 上記のような環境で仕事をしていたことも、今の諸々に繋がることがあります。
… 当時は、日本にいるのに、周りは外国人ばかりで 日本人の方が圧倒的に少ない環境(職場)で 年中 終日を過ごすという、なんとも おもしろく楽しい職場でした!…超 激務でしたけど。。
(以下 ひきつづき、日本語教師での経験から繋がったことです。)
① 習得方法(対象は大人)
特に学び始めの時期など、、子どもであれば 言葉を浴びて イメージや感覚だけでどんどん吸収していくところを、大人でも 全く同じようにしようとすると、却って(マイナスな意味での)遠回りになっているように見受けられることも 少なくはありませんでした。
もちろん、そうでない人もいたり、そのときの状況等によって 感覚や気持ち的な方が響きやすい場合もあり、それらのバランスは必要ではあるものの、
大人になってから学ぼうとする場合、 はじめに ある程度 その概念や概要を把握したり、理論的な方から入った方が、結果的にはスムーズに そして早く習得しているように見受けられることは 多々ありました。
何でもそうかとは思いますが、習得しようとすることと全く関係なくても、それまでの自身の過去のあらゆる経験や 無意識にもっている概念(言語等の場合は 母国(語)など)などの影響は それなりに大きく、意図しないところでマイナスに働くこともあれば、思いがけず いろいろ繋がったり 相違点の比較などから 分かりやすくなることもあります。
ですから、ある程度の概略など(型・文法)を 先に把握して進めた方が、感覚のみで習得しようとするよりも 理解もスムーズで、結果的には 早く、正しく綺麗な言葉が使えるようになることが多い印象でした。
(余談)(※ ココを押下すると 内容が開きます)
また 少し話が逸れますが、、ふだん全く無意識に使っている日本語にも、私たちが中学や高校の英語の授業で習ったような “文法” が ちゃんとあります。(…例えば日本語の”動詞”には「 i ます動詞 / eます動詞 / 例外動詞 」があり、そこから「可能のかたち」「受身のかたち」などに変換するときも、規則性があり··etc…(…懐かしい!笑)
→ これらも私の中ではアコに繋がっています。

あくまでも 私個人の感覚になりますが、こうしたことは 音楽などでも 同じ場合もあるのではないかなとも思っています。
音楽となると、はじめから 自然に 自身の中から湧き出てくるものとされ、フィーリング・感覚に 強くフォーカスされたりすることもありますが、私自身が教わる側のときには そうなると難しく感じてしまうこともあります。つまり、もちろん それができる人もいる一方で、私の場合は、はじめは 何かパターンをいくつか示してもらったり、その表現の仕方(客観的にも分かること)を 先に教えてもらった方が 理解も進みやすく、それからの方が広がりやすくなったりします。

音感が優れている方や 感覚(のみ)で強くアプローチされる方には、このことが なかなか伝わらないようで、「“分からない”ということを分かってもらえない」ということも たびたび起こります(※あくまで私個人の経験です)。
…なんというか、私にとっては、通常は “そもそも知らないこと”は いくら考えても分からない というのと同じような感覚にも近くて。。例えば、ダンスで 突然に「音楽に身を任せて体を動かせば大丈夫!」とか、絵で「この風景を自分が感じるまま自由にキャンバスに描いてみたら良いよ!」と言われるのと同じような感じで、、私にはムズカシく…。。
また、個人の趣向等にもよりますが、分かるまでの過程を楽しむという側面もある一方で、
ある程度の目的までは(先に)到達して、そこから弾ける曲の幅を広げたり、どのように弾きたいかや奏法をどう使っていくか等を考えたり、演奏することで自分や周りの人も楽しめるようにするために より多くの時間を費やすことで、面白さの幅を広げる という考え方もあるかなと思っています。
② 人や そのときによって異なる響き方
人によって 何がどう響くかは異なり、吸収の仕方もさまざまで、それらに影響を与えることのいくつかには たとえば次のようなことがあげられそうです。
- タイミング
習得度合いや、気分、環境などなど。
…状況に合った最適なタイミングで次の目標や課題が掲げられると 吸収しやすくなります。 - 前提(常識·あたりまえ)となっている事柄
母国や それまでの生活環境・経験によって、常識やあたりまえは それぞれ異なります。
…ある国(人)には常識であることが そうでない国(人)もいたり、そもそもその感覚や概念がない場合もあり、その場合は、そういう概念があるということから知るきっかけが要ることもあります。
(余談)都合による解釈(※ ココを押下すると 内容が開きます)
無意識に自身の都合に合わせて解釈していることもあります。 つまり 無意識のまま、自分の都合の良いことだけが耳に入っていたり、自分にとって容易に分かる範疇で思考を停止したりしていて、聞こえていないこともあったりします。だから何かを伝える側のときは 大事なことは何度も伝える必要もあり、受け取る側のときは 相手の意図を もう一歩踏み込んで聞こうとする姿勢が必要な場合もあるように感じます。
当時、これらは 語学学習の場面よりも、日本(=学生にとっては 外国)での生活面で ときどき見受けられる光景でした。

当時は、思いがけず“そもそも”のところで通じておらず、私自身には当たり前で 無意識にあったことが、相手には当たり前ではないことを認識したことも たびたびありました。…だから、何度伝えても伝わらなかったのか…!と。

これらは、発信側のときも受信側のときも 意識すると、それぞれの一助になるのかなと思います。
つまり、何かを伝える側のときは、さまざまな角度からのアプローチや例(例え)、引き出しや選択肢があると より良いのかなと思いますし、
自分が受け取る側のときも、自分が今どのような状況かを 客観的に俯瞰でも見ることができると、理解するときなどの助けにもなるかなと。
いずれにしても 相手をよく見ることなのかなとも思います。
③ 手段と目的の意識 / いろいろな目的
在籍していた学生は、主に 先に書いたとおりなので、将来 日本語を使っていろいろやろうとしている方々でした。ですから、習得は通過点でありながらも、日本語を正確にしっかり使えるようになることが目的。
その一方で、一般的な夏季・冬季休暇時期の特定期間のみ 日本語学校に通学する方々は、数週間程度の短期語学留学という名の旅行者(?!)や、海外(=日本)旅行者が主。ですので、短期間で日本語に触れ学ぶことと同時に、語学学校へ通うという“体験・イベント”としての要素が強め。
詰まるところ 目的はさまざまで、また、長い目で見たときに、日本語が 手段のひとつとなるのか(学んだ言語を将来的に手段として使う用いることを念頭に置いて学んでいるのか)、 それとも それを学ぶこと自体が目的(何かを”学ぶ”のが趣味だったり アクティビティ要素強め)なのかという視点もあったり。
どちらにも それぞれの良さや楽しさがあり、完全に分かれるわけでもなく、両方の要素を入れてバランスはとったりもします。
そういうわけで、前者と後者では、授業内容も大きく異なりました。
(余談?)授業内容の違い(※ ココを押下すると 内容が開きます)
ある程度の期間(と言っても、就学ビザの最長在留期間(2年以内))で、正しく綺麗な日本語を使えるよう、全くゼロの状態~基礎~中·上級まで進めていけるよう、全体をみて体系的に学習カリキュラムが組まれています。
後者は、1回(1コマ)の授業で完結する内容が主体。
たとえば、自己紹介の日本語、お店や旅行で使うときや 道を訊ねるときに使う日本語など、1日1テーマで完結という感じです。こちらはアクティビティや思い出というような要素も 前者よりも強くなり、インパクトのある一時的な楽しさにも より重きが置かれていた印象です。
他には 個人クラス等で、例えば 海外赴任先として日本に滞在している方や、そのご家族の方が通われている場合など。その場合は、先ずは取り急ぎ必要な生活で使う日本語を学び、そこから本人の意向等も踏まえて進めていた記憶がありました。
これらもアコーディオンに(きっとそれ以外にも)置き換えることができます。

私の場合は、自分自身が生徒として習う側のときは、
長期的な視野(先の例では 前者の就学ビザの学生の感じ)を意識していました。
早くいろいろな曲をスラスラ弾けるようになりたいとは思いつつも、私なりの基礎をもって ひとつひとつ進めていった方が 応用も効き、ゆくゆく幅も広がりやすく 長く深く楽しむことができるだろうなぁと漠然と感じ、それに加えて 私自身は音楽の素養やセンスがある訳でもないこともあり、自分自身に合うと思われる習得方法を、アコとは全く関係のない自身のそれまでの経験から考えたからです。
担当させていただいているクラスのレッスンでは、
受講される方のご希望(※)があれば 先ずはそれに沿うようにします。特になければ、理想は ハイブリッドでできたら良いのかなとも思っています。長期的視野は常に入れつつ、そうしたなかで短期的にも楽しめて…というような感じです。

(※)クラスの方のご希望で「とにかく この1曲だけ」という場合のときも、その方のその時の目的に差し支えの無い範囲で、私は少なからず長期的な視点も意識しています。
というのは、続けることで、長い期間を通して気付けたり分かってくることがある楽しみや、1曲を探求していくことで感じられる面白さもあるので、それらが伝わると良いなぁとも思うので。より一層 アコーディオンを楽しむために、長く楽しめる方法・方向にも繋がると良いかなぁと感じています。
また、奏法についても同じようなことが言えるようにも思っています。
つまり、奏法を学ぶときに、奏法を使うことで演奏の幅を広げることを目的としているか(その先を見ているか)、それとも 奏法を学ぶことだけを目的(ゴール)としているのか、というようなことです。
私は はじめから 前者(長期的視野?)を 結構 意識していました。つまり、奏法を学ぶのは、その先の演奏で 奏法を効果的に使うことで 演奏の幅を広げるためのもので、自分がこう弾きたいと思ったときに使える引き出しを増やしておくためのものという認識でした。

ですが、これまた別の経験上、私の場合は、奏法自体を学ぶことのみに集中する時期があった方が 効果的・効率的で良いことも なんとなく感じていたので、一旦は 奏法を学ぶことだけに集中して(※でも、その先の目的を 永遠に忘れてしまうことのないようにメモ-記録に残してました!)、レッスンに集中していました。
ひとりごと
冒頭に書いたように、アコとは全く関係のない経験から繋がったことは いくつもあり、上記はそのうちの 更にその一角です。
今回は過去の“仕事”からのことを書きましたが、仕事に限らず もっと身近にも、たとえば 偶然立ち寄ったお店や その店員さんだったり、久々に行った病院の医師や看護師さんたちだったり… 日常生活の中にも 思いがけないところで繋がることは多々あります。
逆に、過去の経験が 固定概念になってしまうこともあるかもしれず、それはそれで気を付けなければならないものの、
今回書いたことは 歳を重ねてから何かを始めたり、年を重ねていくことにより 感じられる面白さや広がりでもあり、ふとしたときに このように感じるコトができるのも なかなか嬉しい気付きのように思います。
私の場合は こうしたことをより強く感じられるもののひとつがアコで、人それぞれ そういうものがあるのかなとも想像しています。

アコは それ自体 = 楽器の仕組みから、年齢や楽器経験に関係なく 始めやすく、かたちになり、しかも 活用へ繋げられる楽器ですから、歳を重ねてから挑戦する魅力も満載で、やりがいもあります!
今までの経験が 姿を変えて アコーディオンに繋がっているように、今の このアコーディオンでの経験も もしかすると 今後 思いがけないところで いつかの何かに繋がることもあるのかもしれません。
そう想うと、歳を重ねたときに何かを始めたり、また 今していることを長く続けたりすることの楽しみが、より増してくる気がします。そう感じられるものがあるのも、ありがたいコトだなぁと思います。
♪ レッスンのご案内は、▶ コチラ から
♪『レッスン』関連の記事一覧は こちらから ♪

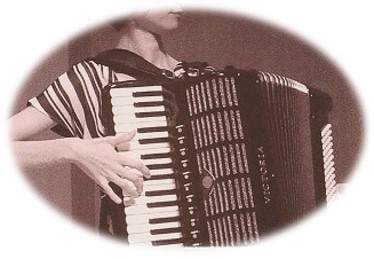

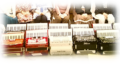

コメント