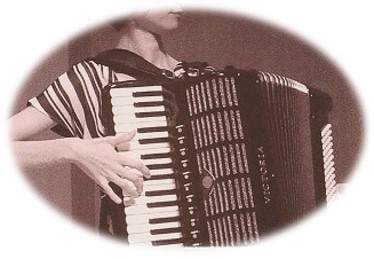どのような場面でも アコーディオンは、小さな子どもたち~ご年配の方々まで、あらゆる年齢層の方々を惹きつけます。
それは、あたたかく華やかな「音色」とともに、次のようなことをはじめとし、多くの魅力を持ち合わせているからだと思います。
というわけで 今回は、アコーディオンの「音色 “+α”」の魅力、つまり、音色 以外 の 素敵なところに焦点をあててみます。
目で見る楽しさ
アコーディオンは、奏でる音色や音楽を「耳で聴く」のはもちろん、「目で見る」楽しさもあります!
演奏姿の楽しさ

蛇腹を動かしながらの、右手-鍵盤と 左手-ボタンの指さばきは、見るのも楽しいです。
しかも、その蛇腹や、鍵盤とボタン(手もと)も、真正面に位置しているので、お客さまから それらの動きも よく見えます。
楽器本体の美しさ
楽器本体や蛇腹の色・模様や、フロントグリル(鍵盤と蛇腹の間のカバーのような部分)のデザインなども、楽器によってさまざま。
まるで楽器の衣装のように綺麗で 目を引きます。

自由度の高さ
アコーディオンはいろいろな意味で、自由自在です!
演奏しながら自由に動ける

楽器を抱えて演奏しているので、移動し(歩き)ながら演奏できます。
弾きながら ちょっとしたスペースを見つけて移動したり、
状況に応じて、お客さまの近くへ行ったり、会話のジャマにならないよう 人混みを避けて離れてみたり、
移動し(歩き)ながら、音量を調節しながら(蛇腹の動かし方で随時音量調節可)、演奏できます。

以前に 屋外イベントのBGM演奏で、主催者さんから「天候が怪しいときや 急に雨がパラついたときも、すぐに屋根のある所へ移動しながら そのまま演奏してもらえるので、天候に左右されなくて(演奏中止にしなくて済んで) 助かります!」と、仰っていただいたこともあります・笑

演奏中も お客さまの方を向いている
弾いているときに 自身の手もとや楽器を見ることは あまりなく(…そもそも楽器の位置的に、自分の手もとは 見にくい&見えないため!)、演奏中は顔を上げているので、
聴いてくださる方々と目を合わせたり、周りの反応を見ながら演奏できます。
屋内外も問わず、どこでも演奏できる

どこへでも持ち運べる楽器なので、屋内・屋外を問わず、また、ステージ等だけでなく、会場内の どちらでも演奏できます。
そして、事前の会場準備も特にありません。楽器は奏者が持参するので、楽器の設置準備等やスペースも要らず、音響等の設備も無くて大丈夫。音量も 奏者自ら蛇腹の動かし方で 調整できます。

私の場合は、ふだんから 立奏※(立って演奏) & 暗譜での演奏なので、椅子や譜面台なども不要です。
これは準備有無の云々だけでなく、(譜面台を置かないことで)楽器等が 譜面台に隠れて お客さまに見えなくなってしまう部分も一切無くなり、この演奏スタイルは 聴いてくださる方に より一層この楽器をお楽しみいただけるようにも思います。
※座奏(座って演奏)もできます!

数年前のコロナ禍のときも、アコーディオンは 心配ご無用な楽器でした。
というのも、コロナ禍に徹底された以下のようなコトは、アコ演奏時に もともとしているコトだったからです。
…つまり、、①非接触 ⇒ 使用するのは自身の楽器のみ。 ②3蜜(密閉·密集·密接) 回避 ⇒ 移動しながら演奏できるので、演奏中も奏者自身で自在に回避。 ③飛沫NG ⇒ 手だけで演奏してますよ、、…というふう。もとから、コロナ禍仕様(?!)な感じの楽器でした!
そして、何より・・・
たった1台(1人)で メロディ+ 伴奏を同時に弾くことができ、且つ、持ち運べる!!
これが最大の特徴のひとつかなと思います。
『たった1台(1人)で メロディ+ 伴奏を同時に弾くことができ、且つ、持ち運べる!!』
「1人でメロディと伴奏を同時に弾ける楽器」は、いくつかあります。また、「持ち運べる楽器」も、たくさんあります。
ですが・・・
「1人でメロディと伴奏を同時に弾くことができて」+「持ち運べる」という、これら両方を併せもつ楽器は、おそらく アコーディオンのほかには 見当たらなさそうです!
ひとこと
パッと簡単に思い付くだけでも、アコーディオンは 音色に加えて こんなに いろいろな魅力のある楽器です。…もう少し考えたら、もっとあると思います!
あらゆるシチュエーションで活躍できる要素も備わっていて、また、弾く場合も 個人の趣味に留まらず、活動の幅も広く、実際に活動しやすい楽器です。
また、弾くのは難しそうと思われることもありますが、特に左ボタンは とても弾きやすい配列·仕組みになっていて、楽器経験がなかったり 音楽理論等を知らなくても ちゃんと伴奏を奏でることができます(左ボタン配列の効率の良さをお伝えすると 驚かれることもよくあります)。
ですから、音楽·楽器経験や年齢も関係なく、お子さまからご年配の方まで、いつからでも始められますし、ひとつひとつ進めていけば どなたでも弾けるようになります。
聴く(音色)も 見る(楽器・演奏姿)も、はたまた 弾くことも、すべてに いろいろな魅力が 盛り沢山に詰まった楽しい楽器。こうした魅力や楽しさが、より多くの人に伝わって、身近に触れる機会がたくさんあると良いなぁと思います!
♪『アコーディオン演奏』関連の記事一覧は こちらから ♪
♪ レッスンのご案内(まとめ)は、▶コチラ から
♪『レッスン』関連の記事一覧は こちらから ♪