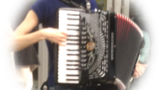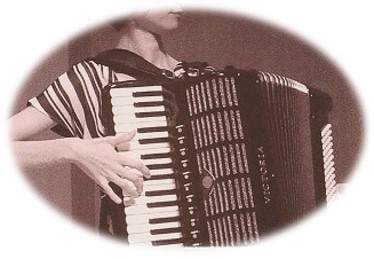今月は 私にしては珍しく、「子ども向け」に演奏させていただく機会が つづきました。ひとつは とある保育園での音楽鑑賞会として数回の演奏、もうひとつは 絵本原画展での ちょこっと演奏です。
子どもに携わる仕事や活動をされていて アコーディオンを弾く方は 少なくないので、とくに前者(保育園 音楽鑑賞会)のお話をいただいたときは、嬉しさやありがたさと同時に “私で大丈夫なのだろうか…“という気持ちも過ってしまったものの、
子どもたちに楽しんでもらうことはもとより、私なりに アコーディオンならではの内容にできたらと、曲目や構成を考えました。
というわけで ここからは、今回関わらせていただいた保育園(以下、園)での、私なりの 小さな子どもたちへ向けての演奏会のことを書いていきます。
選曲にあたって…
今回の園での演奏は、とあるところを経由していただいたお話だったのですが、
もともとのご依頼は「音楽鑑賞会」ということのみ(楽器指定は特になし)だったそうです。
ただ、経由したところの音楽担当の方が、いろいろな楽器の選択肢があるなかで「アコーディオン」を 思い付いてくださり、このような貴重で嬉しい機会をいただけた次第でした。
未就学児への演奏ということで 右も左も分からない私にとって、これら2つの要素は、選曲や構成のヒントや軸となりました。

つまり今回は、その場をより良い雰囲気にするための演奏とも少し異なり、「音楽鑑賞会」であること、
そして、いろいろな楽器の中からアコーディオンを選んでくださったことから「アコーディオンならでは」も出せたらと 改めて意識したところ、構成や曲目なども考えやすくなりました。
ふだんの選曲での 私の視点
ちなみに、特に子ども向け等というわけでなく、ふだん アコーディオン演奏の機会をいただいたとき、私の場合は 基本的には 次のような視点を踏まえて演奏曲を選んでいます。
- 聴いて楽しい(耳)だけでなく、ジャバラや指さばきなどの演奏姿で 目でも楽しめる曲
- スタンダードベースアコーディオンが活きる、いろいろなリズムの曲
- 楽器の魅力が より伝わりやすく、聴いていて楽しい”アコーディオンの曲”
構成を練るにあたって…
今回は 未就学の子どもたちだけ(園児)を対象にした音楽鑑賞会ということもあり、先に挙げた2つの要素や ふだんの選曲での視点をもとに、次のような いくつかの観点も意識しました。
- ① 曲目の区分け
- ② 楽器のこともシンプルに
- ③ 音楽的な要素
- ④ 小さな子どもたちに親しみやすく楽しめるように
それぞれ、もう少し具体的に書いていきます。
① 曲目の区分け
子どもたちに親しみある曲と、ちゃんとしたアコーディオン曲の、両者をバランス良く入れるよう意識し、また、明るく軽快な曲を多くしました。
- 子どもたちが歌える曲〈※掴み〉
→ 曲目:アンパンマンマーチ、さんぽ(トトロ)、コンコンクシャンのうた(童謡)、きらきら星 - 季節の曲、耳にしたことのある曲〈※親しみやすい曲〉
→ 曲目:フニクリフニクラ(通称:鬼のパンツ)、ひなまつり、だんご三兄弟 - アコーディオンの曲〈※アコーディオンの特徴が より活きる/いろいろなリズム〉
→ 曲目:帰ってきたつばめ(ワルツ)、ジョリーキャバレロ(2ビート)、オレグァッパ(タンゴ)、マニアンテブギ(ブギウギ)
② 楽器のこともシンプルに
目の前で アコーディオンを見られる珍しい機会。楽器のことが少しでも分かると より楽しめるかなと、できるだけシンプルに 次のようなことも伝えてみました。

- 蛇腹のこと
… 蛇腹を動かしながら弾く楽器。
蛇腹の動きで音の大きさや強弱も変わる - 音色スイッチのこと
… 1台でいろいろな音が出る。音の高さが変わる - 左ボタンのこと
… 左も音が出る(笑)。いろいろなリズム・場面を表せる
③ 音楽的な要素
音楽鑑賞会ということで、音楽的なことも体感してもらえたらと ごく簡単に盛り込みました。
- いろいろなリズムや拍子 (ワルツ・2ビート・タンゴ・ルンバ・ブギウギなど)
- 音の大小や 音色の違いなど
- 曲のイメージ
④ 親しみやすく楽しめるように
小さな子どもたちに アコーディオンとの時間を飽きることなく楽しんでもらえたらと、このようなことも心掛けました。
- 演奏に合わせて、子どもたちも一緒に歌ったり、体を動かしたり
- 合間のお話は、問いかけたり クイズのようにしたり
- 近々の季節イベントの曲も盛り込む
- 話すときは ゆっくり、動きは 大きく
進行・展開は 気持ち早め - 演奏する側(私)も 一緒に楽しむ

この「小さな子どもたちに、親しみやすく楽しめるように」の諸々は、少し前までこの年齢層の子育てをしていた友人たちや、保育士の知人・友人からのアドバイスなどです。
はじめは どのような曲に馴染みがあるのか等を訊ねていたのですが、それは園などによっても異なる面もありそうなことも分かり、、併せてチラッと教えてくれていたこうしたポイントが とても役立ちました!
演奏曲目や構成など
以上のようなことを 私なりに掛け合わせて、演奏曲目や構成は次のようにしました。
こちらが、今回の私の 小さな子どもに向けたアコーディオン演奏(アコーディオン ソロ @保育園の芸術鑑賞会として)の 大まかな内容です。

小さな子どもたちに 飽きずに集中して聴いてもらえるように…、
全体の流れは、☆子どもたちが知っている曲(※ 歌える曲は歌ってもらう)☆ と、ちゃんとした★アコーディオン曲(聴いてもらう)★を ほぼ交互に演奏し、
また、曲と曲の間には 楽器のお話なども ごく簡単に盛り込み、それらがその前後の演奏曲で活きる(繋がる)よう意識しました。
演奏曲目と その意図
- ☆『アンパンマン マーチ』
…(掴み)初めましての楽器(&私)が、子どもに馴染みある曲で 親しみやすくなれば - ★『Retourdes Hirodelles』(アコーディオン弾きには有名な曲/ミュゼットワルツ)
※ 楽器を間近で見て 生音を感じられるよう、子どもたちの目の前を歩きながら演奏。
鳥さん(つばめ)が 高いところや低いところを飛んでいるイメージも - ☆『さんぽ』
… 子どもたちが全員元気に歌える曲(一旦、子どもたちの息抜きに!?)
- ☆『だんご三兄弟』(次の曲への導入を兼ねて短めに)
★『Ole Guapa』(コンチネンタルタンゴの代表曲の1つ/タンゴ)
※ 蛇腹の動かし方で、音の大小(f/p)や強弱などを表現することもチラッと伝えて。
… 親しみやすい曲調の曲を導入とし、そのまま繋げて タンゴの名曲へ
- ☆『コンコンクシャンのうた』
※ 音色スイッチによる音の違い。
歌に出てくる動物によって音色を切り替えることで、音の違いを分かりやすく
- ★『Jolly Caballero』(スタンダードなアコーディオン曲(P.Frosini作曲)/2ビート)
※ 音楽を楽しみながら、ちゃんと聞いてもらえたら。
… 蛇腹の動きにも注目。ベローシェイクの時は 子どもたちはダンス。
曲の途中からは、アコーディオンの音の大きさに合わせて手拍子(ラデツキー行進曲のように) - ☆『きらきら星』
※ 左ボタンでのいろいろなリズムを、子どもたちもよく知っている1曲で展開。
… いろいろなリズムを お星さまの簡単な物語に乗せて。そのリズムに合わせて 体を左右に揺らしたり足踏みしたりも
- ★☆『Funiculi Funicula (通称:鬼のパンツ)』『ひなまつり』
… 季節の歌で馴染みがありながら、アコーディオン用の編曲で(編曲:伴典哉@トンボ教本)。 - ★『Magnante’s Boogie』(C.Magnante作曲のアコーディオン曲/ブギウギ)
… 曲調もノリの良い曲。左のボタンと蛇腹操作で ブギウギのリズムと、右手が鍵盤上を上下(高⇔低音)に大きく動くグリッサンドなどで 見応えもあり

今回の演奏は、2カ所の園で「2~3歳児…約20分」「4~5歳児…約30分」「2~5歳児…約40分」の3回で、各回 50~70人ずつくらいでした。
ですので、上記の曲目・構成は、毎回これら全てをやったわけではなく、その年齢層や時間などの状況に合わせて、各回 微調整(曲目や 曲の長さ等の増減)しました。
音色+α の魅力
どのような場面でも アコーディオンは、子どもたちも含め あらゆる年齢層の方々を惹きつけます。それは、あたたかく華やかな「音色」とともに、多くの魅力を持ち合わせているからだと思います。
詳しくは、次の記事で 取り上げます。…当記事が長くなりすぎてしまうので…!
…と言いつつも、この「音色+α の魅力」について、その一部を ごくごく簡単に触れてみると、次のようなことをあげられます。

- 視覚での楽しさ
音色を「耳で聴く」のはもちろん、蛇腹と両手を同時に動かしながらの演奏姿や 楽器本体の美しさなど「目で見る」楽しさもあります。 - 自由度の高さ
持ち運べるので 屋内外どこでも演奏でき、また、移動(歩き)ながら演奏することもできます。
そして何より、、
たった1台(1人)で メロディと伴奏が同時に弾けて、持ち運ぶことができます!!
ひとこと ふたこと…
保育園での演奏は 今回 まったく初めてでした。私自身も新鮮で、大変貴重で ありがたい経験となりました。
園での演奏
保育士の皆さんは、
終始 子どもたちひとりひとりに気を配りながらも ずっと笑顔で、演奏中も 自然と盛り上げてくださったり 静かにさせたり。ご自身も子どもたちと一緒に楽しんでいるように見せながら、広い視野で全体を細やかに見ていらして、
子どもたちと接するプロの方々の こうした姿を目の当たりにし、良い刺激をいただきました。
子どもたちは、
元気で可愛く、演奏にもお話にも よく反応してくれました。聴いたことのないであろうアコーディオン曲を聴くだけの時も、意外にも(!?) じっと聴いて·見ていてくれたことは、嬉しい驚きでした。

今回は3回ほど、各回 それぞれ50~80名くらいの子どもたちの前で演奏しました。
通常(大人の場合)は これほどの人数だと結構なスペースを要しますが、そこは 小さな小さな子どもたち!小さなお客さま方のスペースは、その人数でも とっってもコンパクトで、すべてが可愛かったです。
保育園での楽しい思い出のひとつに、今回のアコーディオンもチラッと入れてくれていたら、ふと なにかの拍子に思い出してくれる機会があったら、嬉しく思います。
機会をいただけたこと
今回の演奏は はじめに書いたとおり、経由したところのご担当の方々が アコーディオンを思い付いてくださったからこそ いただくことのできた機会・ご縁でした。
お話をいただいたときには、私自身 初めてのシチュエーション等に驚きや戸惑いはあったものの、子どもたちに楽しんでもらうことに加え、アコーディオン(&私)だからできることは何だろうかと、ふだんとは また少し違った視点で考える機会にもなり、結果 引き出しも増え、とても貴重な経験をさせていただくことができました。

不慣れで至らない点もあったかと恐縮ですが、演奏前後にも裏から覗いて笑顔で手を振ってくれた子どもたちや、「こんなにいろいろな音が出る楽器だと思わなかった / 子どもの馴染みある曲だけでなく、アコーディオン曲もあって良かった / 楽しかった」等々のお声掛けをくださった先生方、当日 本番前の練習時から本番まであたたかく見守ってくださっていたご担当の方々に とても励ましていただきました。
聴いてくれた子どもたちや、一緒に盛り上げてくださった保育士の皆さま、そして、この機会をくださったご担当の方々に、大変感謝しております。
こうした経験を 私自身もひとつひとつ大切に積み重ね、今後の自身の演奏や 担当クラスのレッスンにも 活かしていきたく思っております。
おまけ?)過去の子ども向けの演奏
今までいただいた演奏の機会のうち、子どもたちだけ を対象にした演奏は どんなものがあったかなぁと振り返ってみると…、
結構 前に、小学校での演奏や 合奏のアコパート指導補助、親子の交流ひろば、放課後デイサービス 等々を思い出しました。
なかなか慣れない部分はありますが、そうした場では いつも、子どもたちの周りにいる大人の方々も 温かい笑顔で盛り上げてくださる(!)のも 印象的で。有難く 甘えてしまっている部分もあるかもしれず恐縮ですが、私も楽しく演奏させていただいています。

の
ついでに
子どもたちにとって、また その周りにいる大人の方々にとっても、アコーディオンが加わることで その場が より楽しいひとときとなると良いなと思います。
♪『アコーディオン演奏』関連の記事一覧は こちらから ♪
♪ レッスンのご案内(まとめ)は、▶コチラ から
♪『レッスン』関連の記事一覧は こちらから ♪